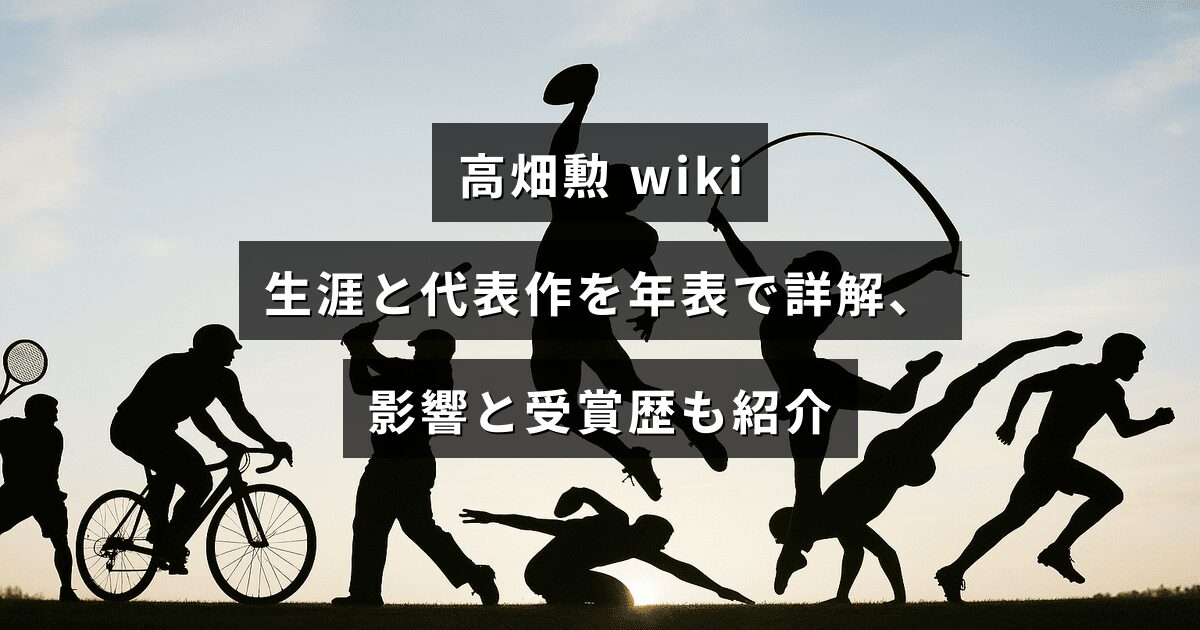高畑勲 wiki — 本記事では、高畑勲のプロフィール(生没年・出身・職業)、学歴、主要経歴と代表作、私生活や評価、そして最新の展覧会・資料発見など、知っておきたい要点が分かります。プロフィールやジブリでの立場、企画裏話、近年の展示や資料発見といった疑問を本文で順に解説します。代表作(『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『かぐや姫の物語』等)や受賞歴、制作手法・影響も本文で掘り下げます。
高畑勲のwikiプロフィール
高畑勲(たかはた いさお)は、日本のアニメーション監督・翻訳家・プロデューサー。戦後から現代にかけて日本アニメ表現を革新した一人で、スタジオジブリ創設にも関わった。
以下はwikiスタイルの要点まとめ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 高畑 勲(たかはた いさお) |
| 生没 | 1935年10月29日 – 2018年4月5日 |
| 出身 | 三重県宇治山田市(現・伊勢市)、岡山で育つ |
| 学歴 | 東京大学文学部仏文科 卒業(1959年) |
| 主な職業 | アニメーション監督、映画監督、翻訳家、プロデューサー |
| 代表作 | 『太陽の王子 ホルスの大冒険』『アルプスの少女ハイジ』『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』『かぐや姫の物語』など |
| 受賞・栄典 | 紫綬褒章ほか国内外で評価 |
所属・職業・肩書き(スタジオジブリ、畑事務所、講師・理事歴など)
関連
- スタジオジブリ所属(共同創設に関与、経営職は辞退)
- 畑事務所代表として個人の窓口業務を運営
- 公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事 等
- 日本大学芸術学部講師、学習院大学大学院ほか客員教授・主任研究員など教育・研究活動に関与
学歴と学生時代
学歴の要約(東京大学・仏文学専攻など)
メモ
- 岡山で学び、東京大学文学部仏文科に進学。1959年卒業。
- 仏文学(フランス詩・文化)を専攻し、翻訳活動も行う(ジャック・プレヴェールの邦訳など)。
学生時代の出会いと影響(フランス映画・ジャック・プレヴェールとの関わり)
在学中に観たフランスの長編アニメーション(『やぶにらみの暴君/王と鳥』の原型)やジャック・プレヴェールの詩に強い衝撃を受け、アニメーション表現への志向を固めた。後年、プレヴェールの詩集邦訳(『ことばたち』日本初完訳)や『王と鳥』の字幕訳など翻訳活動へとつながる影響が確認される。
経歴・実績(年表・タイムライン)
デビュー〜東映動画時代〜Aプロダクション移籍(1959〜1970年代の主な出来事)
| 年 | 出来事 | 所属/肩書き |
|---|---|---|
| 1959 | 東映動画入社 | 演出助手として入社 |
| 1960年代 | テレビ演出デビュー(『狼少年ケン』等)、演出助手 | 東映動画 |
| 1968 | 長編初演出『太陽の王子 ホルスの大冒険』 | 監督(演出) |
| 1971 | Aプロダクションへ移籍(宮崎駿らと行動を共に) | Aプロダクション |
| 1972-73 | 『パンダコパンダ』2作(演出) | 監督/演出 |
日本アニメーション〜ジブリ設立〜代表作の年表(テレビ/劇場作品を年別で)
| 年 | 作品・出来事 | 所属/肩書き |
|---|---|---|
| 1974 | 『アルプスの少女ハイジ』演出 | ズイヨー映像→日本アニメーション |
| 1976 | 『母をたずねて三千里』演出 | 日本アニメーション |
| 1979 | 『赤毛のアン』演出 | 日本アニメーション |
| 1981 | 『じゃりン子チエ』映画版(監督)・TV版チーフディレクター(別名:武元哲使用) | テレコム・アニメーション等 |
| 1982 | 『セロ弾きのゴーシュ』監督(毎日映画コンクール受賞) | 監督 |
| 1985 | スタジオジブリ設立に参加(経営職は辞退) | ジブリ所属 |
| 1988 | 『火垂るの墓』監督 | 監督 |
| 1991 | 『おもひでぽろぽろ』監督(復帰作) | 監督 |
| 1994 | 『平成狸合戦ぽんぽこ』監督 | 監督 |
| 1999 | 『ホーホケキョ となりの山田くん』監督 | 監督 |
| 2013 | 『かぐや姫の物語』監督(アカデミー賞ノミネート等) | 監督 |
| 2018 | 逝去 | — |
私生活・家族・エピソード
生い立ちと家族(出身地、父・兄弟、空襲体験など)
1935年、三重県宇治山田市(現・伊勢市)生まれ。父・高畑浅次郎は教育者で戦後は岡山県の教育長を務めた。
末っ子として育ち、幼少期に岡山での空襲(1944-45年頃)を経験したことが本人の人生観や戦争を描く視点に影響を与えたとされる。
人物像・制作現場のエピソード(遅筆/口述演出/別名使用など)
参考
- 絵は自ら描かず、口述や筆記で演出プランを伝える「口述演出」を得意とした。
- 制作は慎重で緻密だが「遅筆」と評され、予算管理より表現追求を優先する傾向があった。
- 作品によっては別名(武元哲)を使用。現場では生活描写や役者の自然な芝居作りを重視することで知られる。
話題・最新ニュース/トピック
最新ニュース(更新日:2025年08月16日)
(更新日:2025年08月16日)太平洋戦争終結からの節目に伴い、『火垂るの墓』関連の展示や資料公開が各地で行われている。高畑勲に関する研究や企画展の案内が増え、原画・資料の新発見が報じられることがあるため、公式発表を確認の上で情報に接することを推奨する。
注意ポイント
- 展示物や出展情報は展覧会ごとに異なり、報道時点の情報が変更される場合があります。
- メディア報道やSNSの情報は一次ソース(主催者や美術館の公式発表)で確認してください。
展覧会・資料公開(2025年の「火垂るの墓」関連展示や発見資料の注目点)
2025年の展覧会では『火垂るの墓』の制作資料や絵コンテ、発見されたハーモニーセルの初公開等が注目されている(展覧会によって展示物は異なる)。一部メディア報道では、庵野秀明が関与したカットのハーモニーセルが出展される旨が伝えられているが、真偽や出展の詳細は主催者発表で必ず確認してください。
研究・翻訳・関連メディアの最近の動き(書籍・研究会・企画展など)
ポイント
- 高畑作品への学術的関心は継続しており、翻訳研究や表現史に関する論考・書籍が相次いでいる。
- プレヴェール翻訳やノルシュテイン研究など、国外文化との接点を扱う企画も増加。
- ジブリ関係のアーカイブ公開や企画展で、制作過程を検証する資料が順次公開されている。
高畑勲の魅力・評価・影響
作風の特徴と表現革新(生活描写、感情表現、背景との一体化)
高畑はキャラクターの感情を「類型化」しない演出、日常の細部を丹念に描く生活描写、背景と人物の一体化による空気感の創出を追求した。アニメーションを単なる娯楽に留めず、社会的・歴史的主題を真摯に扱う作風が評価される。
受賞歴・批評的評価(国内外の主な受賞と評価の要旨)
関連
- 国内外での映画祭・批評家から高い評価を受け、作品は多くの賞や選考で注目された。
- 『かぐや姫の物語』はアカデミー賞(長編アニメ)にノミネートされるなど国際的評価も顕著。
後進への影響と関連人物(宮崎駿らとの関係、国際的な影響)
宮崎駿とは長年の盟友であり、互いに影響を与え合った関係。若手作家や日本のアニメ表現全体に深い影響を残し、国外の作家や研究者からも注目される存在となった。
高畑に関する情報は「高畑勲 wiki」等のまとめページでも体系的に整理されているため、興味があれば参照するとよい。
よくある質問
高畑勲はどんな人物ですか?
高畑勲は日本のアニメーション監督、翻訳家、プロデューサーで、スタジオジブリの共同創設に関わった重要な人物です。戦後の日本アニメ表現を革新し、多くの名作を生み出しました。
高畑勲の代表作には何がありますか?
高畑勲の代表作には『太陽の王子 ホルスの大冒険』『アルプスの少女ハイジ』『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』『かぐや姫の物語』などがあります。
高畑勲の経歴はどのようになっていますか?
高畑勲は1959年に東映動画に入社し、1960年代から演出助手や監督として活躍しました。1970年代にはAプロダクションへ移籍し、スタジオジブリ設立にも参加。
長年にわたり数多くのアニメ制作に携わりました。
高畑勲の学歴や学生時代の影響は?
高畑勲は東京大学文学部仏文科を卒業し、フランス文学や詩に親しみました。学生時代にフランス映画やジャック・プレヴェールの詩に強い影響を受け、後の翻訳活動やアニメーション表現に大きな影響を与えました。
高畑勲はスタジオジブリでどのような役割を果たしましたか?
高畑勲はスタジオジブリの共同創設に関わりましたが、経営職は辞退し、主に監督やクリエイターとして作品制作に専念しました。
まとめ
ポイント
- 高畑勲(1935–2018)は日本を代表するアニメーション監督・翻訳家・プロデューサーで、スタジオジブリの共同設立に関与した人物。
- 代表作は『太陽の王子 ホルスの大冒険』『アルプスの少女ハイジ』『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』『かぐや姫の物語』など。
- 作風は日常の細部描写と感情の非類型化、背景との一体化を重視し、社会的・歴史的主題を真摯に扱う表現革新で知られる。
- 東映動画や日本アニメーションなどを経てジブリ参加、翻訳・教育活動や受賞歴(紫綬褒章ほか)を持ち、後進に大きな影響を与えた。
- 近年は『火垂るの墓』関連の展覧会や資料公開、翻訳・研究の動きが活発化しており、最新の発見や展示は主催者発表を確認することが重要。
続きが気になる方は公式や展覧会の発表、関連書籍・論考をチェックし、宮崎駿らジブリ関係者の作品や高畑作品の映画を併せて観ると理解が深まります。