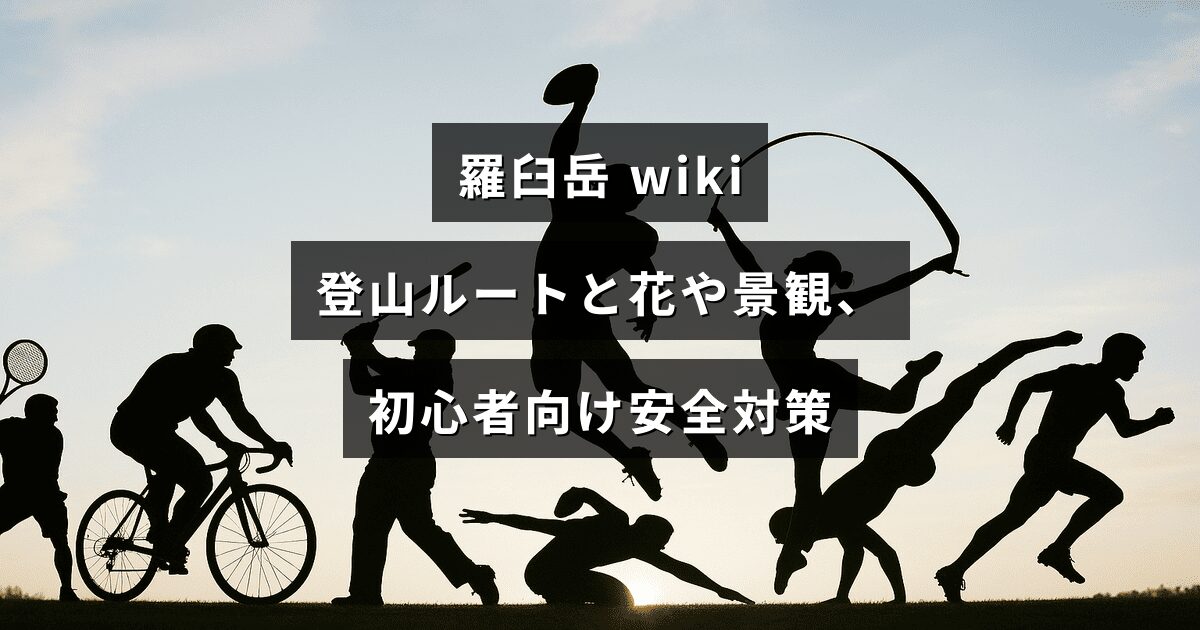羅臼岳 wikiへようこそ。この記事で何が分かるか:基本プロフィール、地質・噴火史、登山ルートや周辺地域との関係、保全・世界遺産化、近年の話題や事故例までを解説します。プロフィールや形成年代、最新の研究やニュースなど、読者が抱く疑問―標高やアイヌ名、火山活動、ヒグマ遭遇の記録―を本文で順に解消します。
羅臼岳のwikiプロフィール
羅臼岳(らうすだけ)は、北海道・知床半島の主峰であり標高1,661メートルの成層火山です。知床国立公園の一部として自然保護と観光の両面で重要な存在で、羅臼岳 wiki や各種山岳ガイドでも紹介されています。
本項では地質・歴史・保全・登山事情などを整理して解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 羅臼岳(らうすだけ)/アイヌ語:チャチャヌㇷ゚リ(chacha-nupri) |
| 標高 | 1,661 m(国土地理院の改訂値、2008年・2014年の測量による変動あり) |
| 所在地 | 北海道・知床半島(羅臼町・斜里町境界) |
| 山種 | 成層火山(溶岩円頂丘・流紋岩〜安山岩質の溶岩) |
| 噴火履歴 | 過去約2300年間に複数回の活動(主に約2,200–2,300年前、1,400–1,600年前、500–700年前)。19世紀末以降の明確な噴火は確認されていないが、1996年に活火山に分類されたことがある。 |
| 保護指定 | 1964年 知床国立公園指定、2005年 知床半島の世界遺産登録に包含 |
| 別称・呼称 | 知床富士、良牛岳(漢字表記の古称) |
所属・職業・肩書き
- 所属
- 知床山脈(知床国立公園)内に位置し、羅臼町・斜里町にまたがる。
- 肩書き・称号
- 知床の代表的な峰の一つ、知床富士の異名を持ち、日本百名山や新・花の百名山に選定されている。
- 役割
- 生態系の核・景観資源・地域観光の目玉としての役割を担う。
学歴と学生時代
地質の“学歴”:成層火山としての形成と年代
羅臼岳は流紋岩質から安山岩質の溶岩を主体とする成層火山で、山頂付近には溶岩円頂丘や比較的新しい地形が残ります。地質学的な調査により、最近約2,300年間で少なくとも三つの活発期が確認されています。
大規模な降下テフラや火砕流を伴った時期があり、地すべりや崩壊地形も多く形成されている点が特徴です。
名称と記録:アイヌ名・古称・歴史的な記述
地元アイヌ語では「チャチャヌㇷ゚リ(chacha‑nupri)=親爺の山」と呼ばれ、知床半島の最高峰として古くから認識されてきました。日本語名の「羅臼岳」や漢字の「良牛岳」などの記録があり、近代以降は観光資源・登山対象として記述が増えています。
羅臼湖や羅臼温泉周辺の記録、切手や観光資料にもその景観が採用されています。
経歴・実績(年表・タイムライン)
火山活動の年代別タイムライン(約2300年の活動史)
| 年代 | 出来事 | 特徴 |
|---|---|---|
| 約2,200–2,300年前 | 第1の活発期 | 比較的大規模な噴火が発生、降下テフラ・火砕流を伴ったと推定される。地形改変が顕著。 |
| 約1,400–1,600年前 | 第2の活発期(プリニー式噴火の痕跡) | プリニー式噴火に相当する降下テフラと火砕流の堆積が認められる。 |
| 約500–700年前 | 第3の活発期 | 溶岩流・火砕流・降下物が堆積。山頂部に新鮮な溶岩地形が残る。 |
| 19世紀後半–20世紀 | 明確な噴火記録は乏しい | 19世紀末以降の大規模噴火は確認されていないが、群発地震や間欠泉活動が観測された時期がある。 |
| 1996年 | 活火山としての評価 | 火山学的調査の結果、活動履歴が整理され、一時的に活火山に分類された経緯がある(噴気活動は限定的)。 |
保護・評価の年表:知床国立公園指定から世界遺産登録まで
| 年 | 出来事 | 備考 |
|---|---|---|
| 1964年6月1日 | 知床国立公園に指定 | 国立公園としての保護管理開始 |
| 1965年 | 羅臼湖畔の切手図案などで紹介 | 観光的価値の広報 |
| 1995–2014年 | 標高の再測定と改訂 | 国土地理院による測量で1,660m→1,661mへと改訂の経緯 |
| 2005年7月 | 知床半島が世界自然遺産に登録 | 羅臼岳を含む地域が国際的に保護対象に |
私生活・家族・エピソード
周辺地域とのつながり:羅臼町・斜里町との関係
羅臼岳は羅臼町と斜里町にまたがり、両町の生活・産業・観光に深く関与します。羅臼町は漁業や観光が基幹産業で、羅臼海域の海産物や温泉、展望塔などと合わせて山の景観が地域ブランドの一部となっています。
国道334号・335号を介してアクセスされ、登山シーズンの宿泊需要やガイド事業が地域経済を支えます。
登山者や研究者のエピソード/ヒグマ遭遇・事故事例
注意ポイント
- 登山道は急傾斜で岩質が脆い区間があり、気象条件の急変に注意が必要とされる。
- 知床地域はヒグマの生息域で、登山者や研究者による遭遇報告が相次ぐため、熊対策(音の出る装備や複数行動など)が推奨される。
- フィールド研究者は堆積物や溶岩形態を手がかりに活動史を復元しており、地域の自然観光ガイドも学術成果を取り入れる事例が見られる。
話題・最新ニュース/トピック
直近のニュース(2025年08月16日現在)
2025年8月16日現在、羅臼岳での新たな噴火の報告はなく、火山活動は顕著な活発化を示していません。登山や観光に関する最新情報、通行規制、ヒグマ情報などは羅臼町・斜里町、環境省および気象庁の公式発表を確認することを推奨します。
羅臼岳 wiki 等オンラインの概要記事でも概況がまとめられていますが、現地情報との照合が必要です。
継続中の研究・保全・観光に関する注目トピック
ポイント
- 火山学:堆積物やテフラ層の年代測定による活動史の精密化、GNSSを含む地形変動の継続観測。
- 生態系保全:登山者管理、ヒグマ対策、希少植物や沿岸生態系との連携保護。
- 気候変動の影響評価:高山生態系・雪形・植生帯の変化の長期監視。
- 持続可能な観光:地域経済と自然保護を両立させるガイド運用や入山規制・教育プログラムの整備。
羅臼岳の魅力・評価・影響
景観・自然美:知床富士としての魅力と観光資源
「知床富士」と称される優美な山容は知床半島の象徴的景観で、羅臼湖や知床五湖から望む堂々たる姿は観光客や写真家に人気です。海と山が近接する特異な地形により、山麓から海岸線まで多様な景観が連続し、温泉や展望地と組み合わせた観光ルートが形成されています。
学術的・文化的評価:日本百名山・アイヌ文化への影響
羅臼岳は深田久弥の日本百名山に選ばれ、学術的な火山研究対象としても重要です。アイヌ文化における呼び名や地域の伝承は文化的価値を高めており、世界自然遺産登録により自然・文化双方の保存と活用が注目されています。
羅臼岳 wiki を含む各種資料は、これらの側面を総合的に伝える入口として有用です。
よくある質問
羅臼岳の標高はどれくらいですか?
羅臼岳の標高は国土地理院による最新の測量で1,661メートルです。北海道・知床半島の最高峰として知られています。
羅臼岳は活火山ですか?
羅臼岳は約2300年間に複数回の火山活動があり、1996年には一時的に活火山に分類されましたが、19世紀末以降の明確な噴火記録はありません。
羅臼岳の別名や呼び名にはどのようなものがありますか?
羅臼岳は「知床富士」や古称の「良牛岳」と呼ばれることがあり、アイヌ語では「チャチャヌㇷ゚リ(親爺の山)」という名前が使われています。
羅臼岳はどの地域に位置していますか?
羅臼岳は北海道の知床半島にあり、羅臼町と斜里町の境界に位置しています。知床国立公園の一部として保護されています。
羅臼岳の火山活動の歴史はどのようなものですか?
約2300年前から3つの活発期があり、特に約2200〜2300年前、1400〜1600年前、500〜700年前に大規模な噴火活動が確認されているものの、近代以降は火山活動が穏やかです。
羅臼岳はどのように保護されていますか?
1964年に知床国立公園に指定され、2005年には知床半島が世界自然遺産に登録される際に羅臼岳も含まれ、自然保護の対象となっています。
まとめ
ポイント
- 羅臼岳は知床半島の主峰で標高1,661mの成層火山。海と山が近接する特徴的な景観を持つ。
- 過去約2,300年間に複数の活発期が確認される一方、直近の明確な噴火報告はなく(1996年に活火山と評価された経緯あり)、最新の火山情報確認が重要。
- 1964年の知床国立公園指定、2005年の世界自然遺産登録を含めて自然・文化双方で高い保護・評価を受けている。
- 登山は急傾斜や脆い岩、気象の急変、ヒグマ遭遇リスクなどがあり、入山前の情報確認と熊対策・装備・複数行動が必須。
- 地質・生態系の研究や持続可能な観光・保全対策が継続中で、地域と連携した管理が求められている。
最新の登山情報・通行規制・火山警報やヒグマ情報は気象庁・環境省・羅臼町・斜里町などの公式発表や公式SNSで必ず確認し、登山は信頼できるガイドや最新の現地情報をもとに計画・装備(熊対策や保険含む)してください。羅臼岳の詳細は羅臼岳 wiki や知床関連の公的資料も合わせてご参照ください。